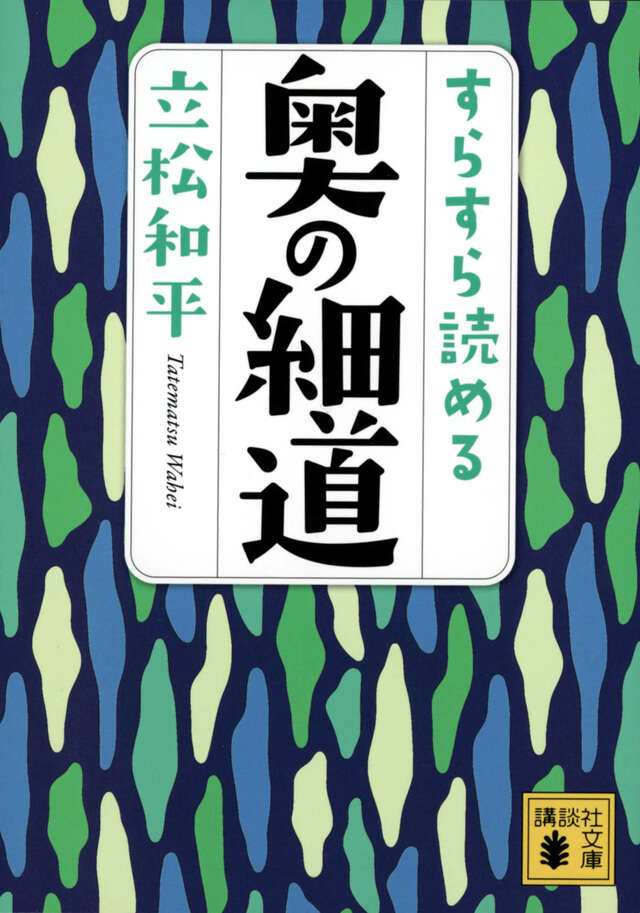「地図のない時代を旅した人たち」──芭蕉と伊能忠敬から見えるもの
先日読んだ『その時あの人はいくつ? 何歳でも歴史は作れる』という本の中で、
55歳から測量の旅に出た伊能忠敬は「江戸中期~後期」、
そして、45歳で『奥の細道』の旅に出た松尾芭蕉は「江戸前期」の人である、ということを知りました。
伊能忠敬が精密地図を作り歩いたのに比べて、芭蕉の旅は、
大雑把な絵図と、人づての情報、そして“旅の経験”だけを頼りに進む旅。
現代のような地図アプリどころか、正確な地図が存在しない時代、旅はまさに大冒険です。
昔から「可愛い子には旅をさせよ」という言葉がありますが、
芭蕉の生きた江戸前期の旅は、まさに“危険”と“未知”の連続。
だからこそ、その旅路には強い覚悟とロマンを感じます。
立松和平『奥の細道』が読みやすい理由
今回読み進めた立松和平さんの『奥の細道』は、単なる現代語訳ではなく、
立松さん自身の解説や随想が添えられている構成で、とても読みやすいです。
「多くの人は土地に暮らしをしばられてきた。
でも、時はごうごうと音をたてて流れ去っていく」
こうした一節を読むと、芭蕉が見た風景や、彼が何を思いながら歩いたのか、
その呼吸まで聞こえてきそうな気がして、自然と“芭蕉の軌跡をたどりたい”という気持ちが湧いてきます。
芭蕉が旅に出るまで — 深川から始まる漂白の人生
芭蕉は若くして地方から江戸・深川へ移り住み、
小さな庵「芭蕉庵」を築き、弟子が集まり、やがて江戸俳壇の中心人物となりました。
そして名句「古池や 蛙飛びこむ 水の音」を詠んだあと、
「時の流れは永遠の旅人。生きてはまた去る年もまた旅人。」
そんな思いから、名の通った俳諧師は、ついに“旅を棲家とする”覚悟を固めます。
お灸で足三里(あしさんり)のツボを温め、
門下生とともに深川を出発したのが3月末。
ここから約150日にも及ぶ大旅行が始まりました。
| NumberName | Place | OpeningLine |
| 1深川 | 東京都江東区深川(芭蕉庵跡付近) | 月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人なり。 |
| 2千住 | 東京都足立区千住(千住大橋付近) | 弥生も末の七日、 |
| 3草加 | 埼玉県草加市 | |
| 4室の八島 | 埼玉県春日部市〜杉戸町周辺(室の八島跡) | |
| 5仏五左衛門 | 茨城県古河市(古河城下・古滝屋五左衛門ゆかりの地付近) | |
| 6日光 | 栃木県日光市(日光東照宮) | |
| 7那須野 | 栃木県那須塩原市〜那須町(那須野ヶ原) | |
| 8黒羽 | 栃木県大田原市黒羽(黒羽芭蕉の館) | |
| 9雲巌寺 | 栃木県大田原市雲岩寺 | |
| 10殺生石・遊行脚 | 栃木県那須町湯本(殺生石) | |
| 11白川 | 福島県白河市(白河の関跡) | |
| 12須賀川 | 福島県須賀川市 | |
| 13安積 | 福島県郡山市(安積地方) | |
| 14信夫 | 福島県福島市(信夫地方) | |
| 15丸山 | 福島県国見町・桑折町周辺(丸山) | |
| 16飯塚 | 宮城県白石市〜村田町周辺(飯塚) | |
| 17笠島 | 宮城県岩沼市〜名取市周辺(笠島) | |
| 18武隈 | 宮城県岩沼市(武隈の松付近) | |
| 19仙台 | 宮城県仙台市青葉区(仙台城址周辺) | |
| 20多賀城 | 宮城県多賀城市(多賀城跡) | |
| 21末の松山 | 宮城県多賀城市・七ヶ浜町周辺(末の松山) | |
| 22塩釜 | 宮城県塩竈市(塩竈神社) | |
| 23松島 | 宮城県松島町(松島湾一帯) | |
| 24瑞巌寺 | 宮城県松島町・瑞巌寺 | |
| 25平泉 | 岩手県平泉町(中尊寺・毛越寺) | |
| 26尿前 | 宮城県大崎市(尿前の関跡) | |
| 27尾花沢 | 山形県尾花沢市(鈴木清風旧跡付近) | |
| 28立石寺 | 山形県山形市山寺・立石寺 | |
| 29最上川 | 山形県大石田町〜村山市〜寒河江市付近(最上川舟運) | |
| 30出羽三山 | 山形県鶴岡市(羽黒山・月山・湯殿山) | |
| 31酒田 | 山形県酒田市(本間家旧本邸周辺) | |
| 32象潟 | 秋田県にかほ市象潟 | |
| 33越後 | 新潟県村上市〜新潟市周辺(越後路) | |
| 34市振 | 富山県朝日町(市振) | |
| 35那古 | 石川県加賀市〜小松市周辺(那古の浦とされる海岸部) | |
| 36金沢 | 石川県金沢市(金沢城・兼六園) | |
| 37小松 | 石川県小松市 | |
| 38那谷 | 石川県小松市那谷町(那谷寺) | |
| 39山中 | 石川県加賀市山中温泉 | |
| 40全昌寺 | 福井県坂井市丸岡町長崎(全昌寺) | |
| 41天龍寺・永平寺 | 福井県永平寺町松岡春日(天龍寺)および永平寺町志比(永平寺) | 越前の境、吉崎の入江を船に棹さて汐越の松を尋ぬ。 |
| 42福井 | 福井県福井市(福井城址周辺) | 福井は三里ばかりなれば、夕飯したためて出づるに、たそかれの路たどたどし。 |
| 43敦賀 | 福井県敦賀市(氣比神宮・気比の松原) | その夜、月殊に晴れたり。 |
| 44種の浜 | 福井県敦賀市色浜 | |
| 45大垣 | 岐阜県大垣市(奥の細道むすびの地記念館) |
私の地元・福井に残る芭蕉の足跡
私の地元・福井県には、芭蕉が訪れた場所がいくつもあります。
たとえば有名な「汐越の松」。
いまはなんと、ゴルフ場の敷地内(福井県あわら市浜坂・芦原ゴルフクラブ海コース付近)にあるんですよね。
また、天竜寺から福井に向かう区間は、
芭蕉は門下生の曽良や金沢からついてきた北枝とは別れ、“ひとり旅”をしています。
福井の詠まれた地は以下のような場所です。
こうした名前を見るだけで、ワクワクします。
Google Mapで辿ってみた「奥の細道 45地点」

今回、表にまとまっていた45地点をGoogle Map上にマッピングしてみました。
CSVファイルは、表をそのままGoogleスプレッドシートに貼り付ければOK。
Google マイマップで「奥の細道マップ」を作る手順
ChatGPT-5.1 2025.11.22
- Google マイマップを開く
- Googleで「マイマップ」と検索 → 「Google マイマップ」を開く
- Google アカウントでログイン
- 新しい地図を作成
- 「+新しい地図を作成」をクリック
- タイトルを例: 立松和平さん風『奥の細道』行程マップ
- CSVをインポートするレイヤーを作成
- 左側の「無題のレイヤ」をクリック
- 「インポート」を選択
- このあと作る CSVファイル をここにドラッグ&ドロップ
- 場所の列・タイトルの列を指定
- 「場所を表す列」→
Placeを選択- 「マーカーのタイトル」→
NoとNameのどちらか(好みで)
- 個人的には
No + Nameにしたいので、インポート前に Excel / スプレッドシート側で結合しておくのもアリです。
マーカーのタイトルは
No + 地名(例:1深川)
の形式であらかじめ結合してあるので、そのまま読み込めます。
自分で地図に落とし込んでみると、芭蕉の旅のスケール感がよりリアルに伝わってきて楽しいです。
次に福井へ帰省したら…
次回以降、福井に帰省したら、
芭蕉が詠んだ場所を一つずつ訪ね歩いてみたいと思います。
地図のなかった時代に歩いた道を、
現代のGoogle Mapを片手に追体験する──
そんな旅も楽しそうですね。
立松和平(2004)すらすら読める奥の細道(講談社)